【契約の概要】
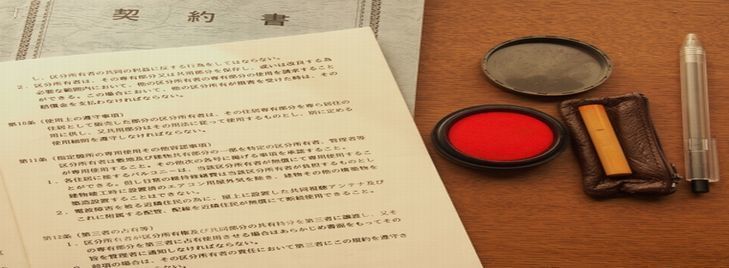
(1)契約とは
企業、個人事業主、個人を問わず仕事または私生活において、契約という言葉を聞きを耳にし、契約書を取り交わす事が多いと思います。
契約とは、一体どのような事か、を考えてみたいと思います。
契約とは、何か?疑問が湧いてくると思います。我々の社会生活においては意識すると否とに関わらず契約を前提に生活を営んでいます。

例えば、マンションを借りて住んでいる場合は、オーナーと賃貸借契約を締結しています。
会社などで働いているときは、雇用契約(労働契約)が存在しています。
また会社に出勤するため、JR、地下鉄、バス等の交通機関を利用するのは旅客運送契約といわれます。
雇用(労働)契約書
コンビニで飲み物、嗜好品を購入するのは、売買契約を締結しています。さらに会社が、運転資金を銀行からお金を借りれば金銭消費貸借契約を銀行と結んでいます。

個人が不動産を購入するために銀行からお金を借りれば金銭消費貸借契約を銀行と結んでいます。いわゆるローンと言われます。
このように、我々は社会生活を営む上において数多くの契約が存在し、多数の契約が存在する中で生活しています。
金銭消費貸借契約
契約の基準となる基本法の民法(債権法)の大改正
令和2年(2020年)4月1日から「民法の一部を改正する法律」が施行されました。
企業の取引や個人の日常生活に深く関わる契約について定める分野である債権法が、約120年振り りに社会経済の変化に対応するように改正されており、令和2年4月1日より施行されました。
民法は日常生活に直接に関係するもっとも基本的な法律です。民法(債権法)の改正により、契約 に関する様々なルールが変更されました。従って従来の契約書の見直し急務となります。
詳細は、弊所ホームページで確認または弊所までご依頼、お問い合わせをお願い致します。
(2)契約の意義
① 契約とは、法的な約束・合意のことを言います。
もう少し詳しく言いますと、契約とは、例えば、ある時計の売買を考えたとき、買主が売って下さい、売主が売りましょうとの意思の表示したときに時計の売買契約は成立します。

すなわち、契約とは、お互いの対立する意思表示の合致のよって成立する法律行為を言います。
講学上の表現のため分かり難い表現ですが、法的な約束・合意が契約です。単なる約束とは異なります。
例えば、友人に親切にすると約束したときでも、法律上の契約ではありません。
法的な合意が契約です!
親切にしなかったとしても友人は、法律上損害賠償を請求することは出来ないとされています。
何故ならば、このような合意・約束は、道徳的に遵守を要求できたとしても、法律的に意味を持ったものではなく、法的に強制するとの性質ではありません。
法律上の強制力を持つことならないからです。
② これに対して、法的な契約は、契約によって「権利」,「義務」が発生する点において単たる約束や合意との違いがあります。
例えば、土地の売買契約において、買主は「1000万円で土地を買いたい」との申込を行い売主が、その土地を売ると承諾すれば、土地の売買契約は成立し、売主は、土地を引き渡す義務が生じ、買主は法律上の権利として土地の引き渡しを請求する事ができます。
また、契約は、当事者の申込と承諾という意思の合致により成立します。
契約書の作成は必要とされていません。売買契約であれば、「売ります」との申込、「買います」との承諾の合致にによって売買契約は成立します。
売買契約書を作成しない場合でも売買契約は成立しています。
もっとも、契約の種類によっては、例えば保証契約の様に契約書の作成が必要とされる場合があます(民法446条2項)。
法律で書面の作成が必要とされている場合以外は、口約束・口頭の合意で契約は成立します。
③ ところが、契約を締結した場合には契約書が作成されるのが一般的です。それでは、何故に、契約は口約束でも成立するにもかかわらず、契約書という書面を作成するのでしょうか。
もし契約書を作成しないで、口約束・口頭のみの契約では、契約内容の確認ができません。また、紛争が生じた場合、契約内容の確認や証明ができなくなってしまいます。
人間の記憶は、時間の経過とともに薄れて行き、あいまいになって行きます。
そこで、契約した内容を契約書という書面を作成することで契約内容、権利義務の存在が明確になります。契約内容を形に残しておくことができ、契約内容の証明が簡単になり、トラブルが発生したときでも、解決の基準となります。
また、契約書を作成することによって、トラブルを未然に防止することが可能となります。
注目 日本と欧米における契約の見方の違い
① 契約に対する考え方、見方、意識は日本と欧米は全く異なるといえます。
例えば、日本において、取引に際して契約書に詳細に規定した条項を記載しようとすると「水くさい」とか、「当社を信用していないのですか」といわれかねません。
また、詳細な条項や債務不履行があった場合の取り決める事は、相手に対して不信感を表明したことになるから控える事が肝要であり、もし将来に問題が発生したときは、お互い紳士的に協議して紳士
的に解決して行けば良いとの考え方が支配的です。
日本人は、あまり契約書に好意的ではなく、また、裁判も避けたがる傾向があります。

② これに対して、欧米において契約書を作成するときは、一つ一つの条項について詳細に検討し詰めが行われ、交渉がなされ、契約書が調印されます。
契約書に記載されていない事項は、契約の内容ではないとされています。
外資系では、契約書は300〜500ページ位またはそれ以上作成され、契約書を英語と日本語で作成する事が一般的です。
以上の事は、外資系に勤務してときに、痛感しました。
外資の風景
(3)契約の種類
契約には、様々な種類があり、諸々の観点から分類する事ができます。私法の基本法である民法には以下の13種類の契約が定めれています。
例えば、贈与 交換 売買 消費貸借 使用貸借 賃貸借 雇用 請負 委任 寄託 組合 終身定期金、和解が民法に規定されています。この民法の13種類の契約を典型契約、有名契約といいます。
これ以外の契約内容の契約を締結することは、もちろんできます。民法の定める13種類以外の契約を非典型契約または無名契約といいます。
また、 原則として、契約は当事者の自由な意思により内容を定め締結することができます。
しかし全くの自由ではなく、公序良俗(民法90条)や他の法律の強行規定には反することはできません。
したがって、契約書に記載すれば、どのような内容でも有効にはならない事になります。
注目 民法(債権法)が大改正され、令和2年(2020年)4月1日に施行されました。
今回の改正は、120年振りの改正であり社会、経済の変化に対応するものです。約200項目、条文数は300条以上が変更された大改正です。
今回の改正は、新しいルールを創設したほかに判例の内容を条文化したものであり、法律上の概念の平易化や消費者保護の観点に立脚しています。
債権法の改正により、契約に関する様々なルールが変更されました。
従って、従来の契約書の見直し急務となります。各契約の主な改正点を記載します。
詳しくは、弊所ホームページで確認または弊所までお問い合わせ、ご依頼をお願い致します。
★民法の規定する契約の中で代表的な契約の概要は以下のとおりです。
① 贈与契約贈与は、一方の当事者が自己の財産を無償で相手に与える意思を表示して、相手方がこれを受諾して成立する契約です(民法549条)。
簡単に表現しますと、例えば、旅行のおみあげ、お歳暮、お祝い金のように自己の財産を無償、ただで相手方に与える契約です。
財産をあげる方を贈与者といい、財産をもらう方を受増者といいます。 今回の改正で大きな改正点は、ありません。
② 売買契約
売買は、当事者の一方(売主)がある財産権を相手方(買主)に移転しすることを約し、相手方が、これにその代金を支払うことを約することによって成立する契約です(民法555条)。
例えば、コンビニで飲み物を購入する場合、買主は「買います」との意思と売主の「売ります」という意思が合致することで飲み物の売買契約は成立します。

因みに、売買契約は、合意のみで成立し契約書の作成は必要とはされていません。
建物やマンション等の不動産のように高額な場合は、紛争の未然防止のため売買契約書が作成されます。
土地建物の売買契約は必ず契約書が作成されます。
また、今回の改正で売買契約は、瑕疵担保責任の規定が変更され「契約内容不適合」という内容になりました。むずかしい用語です。
例えば、売主が買主に対して契約の内容に合わない、適合しない目的物を引き渡したときは、債務不履行になります。
その結果として買主は、売主に対して履行の追完請求、代金の減額請求、損害賠償請求、契約の解除することができます(民法第562条以下)。また、買主の善意・無過失の要件も不要になりました。
改正により売買契約は、内容が大幅な修正、変更のために契約書の修正や見直しは必要となります。
③ 消費貸借契約
消費貸借は、当事者の一方が種類、品質、数量等の等しい物をもって返還することを約して、相手方より金銭その他の物を受け取ることによって成立する契約です(民法587条)。
例えば、銀行から100万円のお金を借りる場合には、借主が金銭を貸主である銀行から100万円受けとって、後で同じ数量の100万円を返還する場合です。
消費貸借は、金銭の貸し借りである金銭消費貸借契約が代表的です。借りたもの自体を返還するのではなく借りた物を使い、それと同様の物を返すところに特色があります。
今回の改正で消費貸借契約は、従来物を受け取ることによって成立する要物契約とされていましたが、改正により書面による消費貸借契約は物の受け渡しがなくとも合意だけで成立することになりました。
いわゆる、諾成的消費貸借契約の成立を認める規定が設けられました(第587条の2)。
④ 賃貸借契約
賃貸借は、当事者の一方がある物の使用、収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対して、その賃料を支払うことを約することによって成立する契約です(民法601条)。
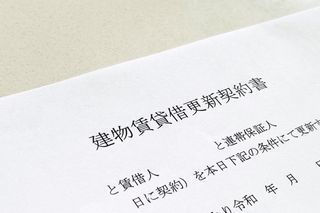
土地、建物、マンション等の不動産の賃貸借が一般的です。例えば、マンションを借りるときに締結される契約が賃貸借契約です。
もちろん、不動産以外の自動車、時計などの動産についても賃貸借契約は、成立します。
貸主(地主・大家)のことを賃貸人(ちんたいにん)といい借主のことを賃借人(ちんしゃくにん)といいます。
建物賃貸更新契約
今回の改正で賃貸借契約は、重要な変更がなされました。敷金について規定が設けられました(第 622条の2)。
また、原状回復義務が規定され、通常の損耗や経年劣化の場合は、賃借人に現状回復義務はないと規定されました。その他に重要な内容が修正、変更、追加されました。
⑤ 雇用契約
雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事する事を約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、成立する契約です(民法623条)。
例えば、会社に雇われるときに締結される契約ですが、雇用契約が成立することによって労働者は使用者である会社の指揮命令に従い、労働力を提供し、使用者は賃金を支払う義務が生じます。
⑥ 請負契約
請負は、当事者の一方(請負人)がある仕事を完成させることを約し、相手方(注文者)がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことをやくすることによって成立する契約です(民法632条)。
今回の改正で賃貸借契約は、重要な変更がなされました。
⑦ 委任契約
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、成立する契約です(民法643条)。
委任は、法律行為だけではなく事務の委託までも含み委託する方を委託者、委託を受けた、頼まれた方を受託者といいます。
⑧ 寄託契約
寄託は、当事者の一方が相手方のために保管すること約してある物を受け取ることによって成立する契約です(民法695条)。
例えば、ホテルのクロークのように、荷物を預かることを内容する契約です。

⑨ 和解契約
和解は、当事者がお互いに譲歩して、その間に存在する争いをやめることを約することによって成立する契約です(民法695条)。
和解は、お互いに譲歩することで紛争を解決する内容に特色があります。
なお、日常生活において示談という用語も民法の規定する和解に該当します。
譲歩により和解契約が成立した場合
契約書のご依頼・ご相談はこちらをクリック

メールアドレスはこちら:m.isogai@s6.dion.ne.jp
▼▼お電話でのご依頼・ご相談はこちら▼▼
TEL:03-4523-8512
(4)契約の交渉の仕方
① 取引先と契約を締結するとき、取引先の相手方である会社が契約書案を作成して提示してくることが多いのではないかと思います。
そのときは、どの様に対応されていますでしょうか!
相手の作成した契約書案を検討することなくサインして会社の実印を押印する。または、こちらで契約書案を審査・検討して当社に不利益な内容はないかを確認する。
そして、当社に不利益な条文の内容があったときは、相手方と交渉をして不利な内容の修正や削除を求める。その代わりに、相手方の要求や条件を認めて行くことが行われると思います。
② 各法律の条文は、法律上の性質として、任意規定と強硬規定に分類することができます。
強行規定とは、その規定を遵守することが必ず要求される規定をいい、任意規定とは、契約当事者の合意によって、その規定の適用を排除することができる規定を言います。
分かりにくい表現ですが、強行規定は、公の秩序に関する規定であり社会生活や経済取引の基本となる内容を定めた規定です。
したがって、契約の当事者が話し合いによって、その規定の適用を排除することはできないとされています。
例えば、結婚は、婚姻届を提出することによって効力が生ずると規定されています(民法73条)、
当事者で婚姻届を出さなくても婚姻は成立する、とはできません。婚姻は、社会秩序を定める強行規定とされているからです。
これに対して、任意規定は、社会秩序を定める規定ではないため、当事者が任意規定の条文内容と異なる取り決めを行うことは何ら問題はないことになります。
例えば、マンション等の賃料の支払い時期に関して、法律上は、月末に後払いで支払うと規定されています(民法614条)。
しかし、家賃の支払い時期は、社会秩序とは関係しないため、これと異なり合意で月始めと定めることができます。
③ 契約交渉に際して、当事者は契約書の内容が自己に有利になるように、任意規定をめぐり当事者双方の様々な交渉や駆け引きが行われます。
例えば、契約書案を熟読し、記載された条文内容をチェックしたうえ、こちらにとって不利な条文内容か否か、また、任意規定または強行規定なのかを判断して行きます。
こちらにとって、不利となっている契約書案の条文内容が強行規定の場合には、当事者の合意によって適用を排除することができないことから、強行規定である事を主張して不利な条文の削除を要求します。
例えば、私の企業法務実務経験から貸室賃貸借契約書には、借地借地法の強行規定に違反する条項がかなり見受けられました。

★ 裁判になれば、その規定は無効となります!
契約書案の条文が任意規定のときは、自分に有利になるように意図し、相手方と話合いの上、こちらにに有利になるような内容、特約を盛り込むようにします。
逆に、相手方が相手方にとって有利な内容、特約を主張してきたときは、自己にとって不利益になりますので、どの程度の影響があるのかを判断し、承服できない内容であれば、相手方に削除、変更を要求して行きます。
当職の企業実務経験から、任意規定においても、損害賠償額の予定、範囲、契約の解除その他において裁判所の判例に反する、強行法規に抵触する契約書の条文が多く見受けられます。
④ 会社、個人事業主を問わず、こちらに不利益な内容の記載された契約書をそのまま締結して不
利な条件を押し付けられている事が非常に多いことを痛感して来ました。
更に、契約締結の交渉は、法的知識を前提に裁判所の判例、行政機関の先例やガイドラインに基づきこちらの主張を行います。
その後は、誠意をもって、落とし所を探しつつ交渉することが肝要と思われます。



交渉の過程 交渉の最終段階 交渉成立(契約成立)
以上が、当職が、非上場企業や1部上場企業に法務部責任者として、相手方である1部上場の某不動産会社、上場の某アパレル会社、外資の某IT会社等々、さまざまな会社の法務部や顧問の法律事務所と交渉してきた経験から、体得した交渉方法の一例です。
その他にも、まだまだ様々な交渉経験をして来ました。
⑤ また、会社、個人事業主を問わず、こちらに不利益な内容の記載された契約書を審査、検討をしない状況でそのまま締結していることが、非常に多いことを痛感して来ました。
これは、法務を担当する社員や法務部門がないために相手方と対等な交渉や話合いができず、こちらの正当な法律上の利益が確保されていない状態です。
契約当事者は、法律上は対等な立場ですが、法務部が無いために法的利益の確保ができない状況であり、正当な法律上の利益を確保するため法的支援の重要性、必要性を痛感しております。
予防法務の専門である弊事務所は、その役割を担いたいと思っております。
(5)契約を締結する場合の注意事項
① 契約の相手方
契約を締結するときの相手方は、株式会社、特例有限会社、合同会社等の法人と個人が想定させますが、現実の取引においては、契約の相手が会社であるのか個人であるのかが明確でない場合があります。
例えば、「Y商店」という看板を掲げて広く経済活動、商売を行っていた場合であってもY商店が会社ではなく、Y自身が営んでいる個人事業の場合もあります。
この場合の契約の当事者は、「Y」自身であり、「Y商店ことY」が契約の相手方になります。
さらに、「X商事株式会社」との商号を使用し、名刺に書いてある場合でも、実際には会社の設立手続きをおこなっておらず、会社の設立登記自体がさなれていない場合もあります。
いわゆる、架空会社といえます。
このような、架空会社の場合は、会社が存在していない以上、契約の相手方は個人となりますので注意が必要です。

したがって、契約交渉途中において、本当に会社であるのか等の疑問が生じたときは、会社の登記事項証明書、(登記簿謄本)を法務局から取り寄せ確認する必要があります。
もし、登記簿謄本を申請して、商業登記簿が法務局に見当たらないときは、会社自体の登記がなされていない事になます。個人で事業、商売を行っていることが分かります。
法務局
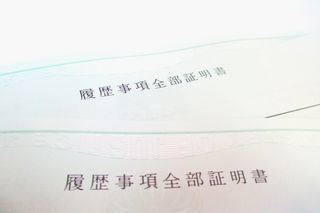
ちなみに、商業登記簿には、株式会社、合同会社等の会社の種類・事業目的・資本金額・代表取締役・取締役・監査役・設立年月日などの会社情報が記載されています。
商業登記簿を確認することで、会社の内容をある程度、知ることが可能です。
登記事項証明書(登記簿謄本)
② 個人が契約の相手方の場合
個人の場合は、住所と氏名によって特定されますので、住所及び氏名を署名または記名した上で押印します。
押印は、市区町村に登録された実印を使用するべきです。認印、シャチハタですと誰でも簡単に手に入れることができるために、無権限者のよって偽造される恐れがあります。
そして、実印の印鑑証明書を添付することで、契約書は当事者である本人の作成によるものとの推定が働くため、本人が作成した事の真正が確保されます。
③ 会社等の法人が相手方の場合
会社や社団法人、NPO法人等の法人と契約を締結するときは、法人は、権利義務を有することができます。しかし実際に活動するのは、会社等にいる役員・従業員です。
そこで、会社に代わって、会社の人間が契約を締結することになるため、契約を締結する権限を有してことが必要となります。
この権限を有する者として、会社の代表権を有する者と会社の代表者から契約締結に関する代理権を与えられた者が考えられます。
a 会社の代表権のある者

代表取締役社長、代表取締役副社長、代表取締役専務等の名称で会社の代表権のある者は会社法349条)、会社の契約を締結することができ、契約の効果はすべて会社自体に帰属することになります。
なお、代表取締役が選任されておらず、2名以上の取締役がいる場合には、各取締役が各自会社を代表して代表権を有していることから、各取締役が契約を締結する権限があります(会社法349条2項)。
代表権のある代表取締役
b 会社代表者から契約締結の代理権を与えられた者
・担当取締役
代表取締役がいる会社においては、代表取締役が会社を代表するため、代表取締役が契約を締結する権限を有しています。
しかし、代表取締役より契約を締結する代理権を授与された担当取締役(代表権のない平取締役)が会社の契約を締結する事があります。
この場合は、会社の契約を締結することができます。契約の効果は、すべて会社に帰属することになります。
もっとも、契約を締結する担当取締役が、契約を締結する権限を本当に有しているか否かは、取引の相手方からは、明確に判断できない場合が多いのではないか思います。
そこで、例えば、委任状等の契約を締結する権限を証明する書面を呈示または交付してもらう事が、こちらの利益確保の観点から重要だと思います。
・支配人
支配人は、商人の営業所において、営業活動を行う商業使用人ですが、営業主に代わってその営業に関する一切の裁判上または裁判外の行為を行う権限を有しています(商法21条)。
従って、支配人は法律でこのような権限を与えられているため、契約の締結権限を有しています。
例えば、支店長等です。
因みに、支配人の選任については、登記事項とされているため(商法22条)、商業登記簿で確認できますので、必ず支配人である事を確認することが肝要です。
・部長、課長
商人の営業に関して、ある種類または特定の事項の委任を受けた使用人は、特定の範囲内の事項に関しては、一切の裁判外の行為をする権限を有するとされています(商法25条)。
したがって、特定事の項の委任を受けた使用人は、契約を締結する権限があります。
例えば、人事部長が人材紹介会社と人材紹介について、業務委託契約を締結する権限を会社から授与されている場合には、人事部長は人材紹介会社と業務委託契約を締結することはできます。
もっとも、契約の相手方は、例えば人事部長に契約を締結する権限があるか否かを明確に判断することは、簡単な事でなないと思われます。

そこで、会社から権限が与えられた委任状を示してもらう、または添付してもらう等の措置をとることが考えられます。
または、代表権のある代表取締役名義で契約を結ぶことが、法的リスク回避の観点からは重要です。
委任状
以上のように、会社等の法人と契約を締結するときは、相手方の契約書の名義人となる締結者が、本当に契約を結ぶことができる権限があるのかがポイントなります。
商業登記簿や委任状等で確認することが、トラブルの未然防止のために必要となります。
④ 会社が契約当事者の場合の記載方法
個人が契約当事者の場合、住所及び氏名を署名または記名した上で押印することで問題はありません。
これに対して、会社の場合には、個人と異なり注意が必要です。
a 本店所在地
会社の本店所在地を商業登記簿の記載のとおりに記入します。
もっとも、会社が当事者の場合であっても、契約を締結する権限を支店長に与えているときは、支店所在地でもよいことになります。
b 商号
会社の商号を商業登記簿のとおり正確に記載します。
正確に会社の種類を書く必要があります。
また、株式会社を商号の前に記載するのか、後に記載するのかも確認し、(株)と省略するする事は避けて正確に記載するべきです。
c 当事者(資格・氏名)
会社は法人ですが、対外的に会社を代表するのは代表機関とされています。株式会社では、代表取締役です。
会社の代表権を有する代表取締役の代表資格を記載して、氏名を記載します。
もっとも、会社から契約締結の代理権を与えられている人事部長は、代理人としての資格を記載し、氏名を書きます。
d 印鑑
最後に押印します。会社の代表者の場合は、法務局に登録してある実印である代表印が後日の紛争を防止するため、相手方の信頼感との観点から望ましいと思います。
しかし、認印を押したとしても契約の効力が否定されることはありません。
ご依頼・ご相談はこちら

TEL:03-4523-8512
受付時間
平 日:9時30分〜19時まで
土曜日:10時〜17時まで
定休日:日曜日・祝日
フォーム,メールによる相談は、年中無休となって
おります。
メールアドレスはこちら:m.isogai@s6.dion.ne.jp

