【著作権とは】
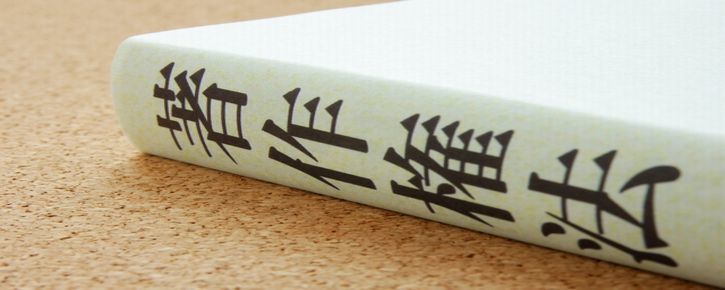
「著作権とは」、と聞かれ正確に答えられる方は少ないのでは?著作権は報道などで良く耳にする 言葉ですか意外にその内容は曖昧なままで、はっきりしない法律用語です。
(1)著作権の意義
著作権は、簡単に言いますと、著作物を保護する権利です。著作物を創作した人を著作者と
言います(著作権法第2条1項2号)が、著作者の人格利益を保護する「著作人格権」と財
産的利益を保護する「著作権(著作者財産権)」から構成されます。
(著作権法第17条)
① 著作権(著作者財産権)
著作権は、著作者の経済的利益を確保、保護するための権利であり、金銭的に損をしない事を
内容しています。
著作権は、以下のとおり12種類の権利に細分化されおり、これを支分権と言います。
著作権は、支分権の集まり であり支分権の束 と言われています。
a 複製権(第21条)
複製権は、著作権の中心的な権利です。著作者は著作物を複製する権利を専有しています。
つまり、著作者は、承諾なく著作物を無断で複製されない権利を有しています。

b 上演権・演奏権(第22条)
著作者は、著作物を公衆に上演し、演奏する権利を専
有しています。
著作者に無断で公衆に上演、演奏されない権利です。
c 上映権(第22条の2)
著作者は、著作物を公に上映する権利を専有しています。上映権は、著作物を勝手に上映されない権利と言えます。
d 公衆送信権(第23条1項)
著作者は、著作物について公衆送信を行う権利を専有しています。著作者に無断で勝手に著作物を公衆送信されない権利です。
e 公の伝達権(第23条2項)
公衆送信された著作物を受信装置を使用して、公衆に見せ聞かせたりする権利です。ラジオ・テレビ等で勝手に著作物を伝達されない権利です。
f 口述権(第24条)
言語による著作物を朗読その他の方法により口頭にて伝達する権利です。例えば、言語による著作物を勝手に公衆に口述されない権利と言えます。
g 展示権(第25条)
美術の著作物または未完成の写真の著作物について、これらの原作品により公に展示する権利です。例えば、美術・写真の著作物を勝手公衆に展示されない権利と言えます。
h 譲渡権(第26条の2)
譲渡権は、著作者に無断で著作物をその原作品または複製物より公衆に譲渡されない権利です。
i 貸与権(第26条の3)
著作者は、著作物(映画の著作物は除外されます)の複製物の公衆への貸与に関する権利です。
貸与権は、著作者の承諾を得ないで著作物の複製物を公衆に貸与されない権利です。
g 頒布権(第26条)
頒布権は、映画の著作物に限り、著作者の承諾を得ることなく映画の著作物を頒布されない権利です。頒布(はんぷ)は、複製物を譲渡または貸与することとされています。
j 二次的著作物の創作権(第27条)
著作者は、その著作物を翻訳、編曲、変形、脚色、映画化し、その他翻案する権利を専有しています。即ち、著作権者に無断で、二次的著作物を創作されない権利です。
★ 二次的著作物は、原著作物に新しい創作が加えられた著作物を言います。
例としてアニメを映画にする、海外の小説を日本語の小説に翻訳する等があります。
原著作物に新たな創作を施した場合は、別個の著作物として著作権法によって保護されます。
K 二次的著作物の利用権(第28条)
二次的著作物の原著作者の著作者は、二次的著作物の利用に関し、二次的著作物の著作者が有する権利と同等の権利を有しています。
つまり、無断で二次的著作物を利用されない権利です。
② 著作者人格権
著作者人格権は、著作者の著作物に対する人格的、精神的な利益を保護するための権利です。(第18条1項、19条1項、20条1項)。人格権とむずかし用語です。
著作権者が、精神的に感情的に傷つけられないようにする権利と言えます。
著作者人格権は、公表権、氏名表示権、同一性保持権に分類されます。
a 公表権
著作者は、その著作物で未だ公表されていない著作物を公衆に提供し、または提示する権利を有しています(第18条)。
無断で公表されない権利、著作者は自己の承諾を得ない公表を禁止する事が可能です。
b 氏名表示権
著作者は、著作者の氏名を公表するかしないか、また公表する場合に実名にするか変名、ペンネームにするかを決定する権利を有しています(第19条1項)。
c 同一性保持権
著作者は、その著作者及びその題号の同一性を保持する権利を有し、著作者の意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けない権利を有します(第20条1項)。
著作物とその題号について、著作者は無断で改変されない権利です。
(2)著作物とは
著作権法によって保護されるのは、著作物です。著作物は著作権法2条1項1号によって次のように定められています。
「著作物とは、思想または感情を創作的に表現しものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものをいう」とされています。
著作物は、以下の要件から成立しています。
① 思想または感情の表現であること。従って、歴史事実やデータの羅列は、著作物ではありません。
② 表現に創作性があること。表現に創造性がなければならず他の著作物の模倣、盗用は創作ががあるとはいえず、著作物に当たらないとされています。
③ 外部に表現されていること
言葉、文字、音、色彩等の方式をとり外部に表現されていなければならないとされます。
従って、アイデアは著作者の頭のある限り著作物ではありません。
④ 文芸、芸術、美術または音楽の範囲に属するものであること。
文芸、芸術、美術、音楽に限定される意味ではなく、広く精神活動全般を意味します。
従って、発明等の産業の範囲に属するものは、著作物ではないことになります。
⑤ 著作権法第10条1項は、以下のとおり著作物を例示しています。
しかし、例示であるため、これに限定されるものでは
ありません。
a 小説、脚本、論文、講演その他言語の著作物(1号)
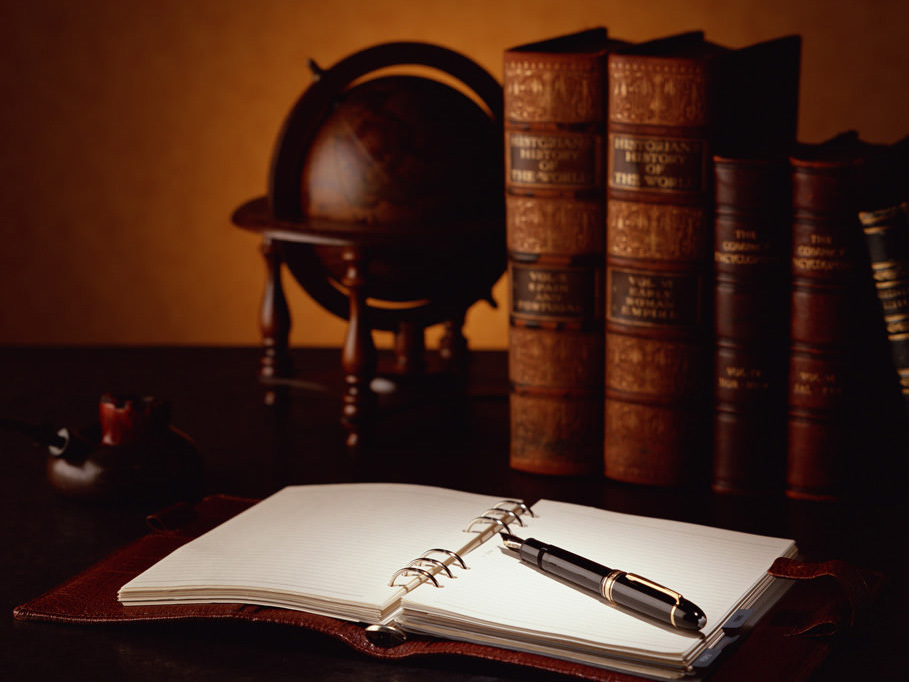
・小説、脚本、作文、詩、俳句、レポート、論文、講演等
b 音楽の著作物(2号)

・ 楽曲や楽曲を伴う歌詞等
c 舞踊または無言劇の著作物(3号)

・ バレエ、ダンス、パントマイムなどの振り付け等
d 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物(4号)

・絵画、版画、彫刻、漫画、書道、茶碗や壷、刀剣などの美術 工芸品等
e 建築の著作物(5号)

・ 建物、庭園、橋など芸術的な建築物
f 地図または学術的な性質を有する図画、図表、模型その他の図形の著作者(6号)

・ 地図、設計図、立体模型等
g 映画の著作物(7号)
・劇場用の映画、アニメ、ゲームソフトの映像、ビデオなどの録画されている動画等
h 写真の著作物(8号)

・写真、グラビア等
i プログラムの著作物(9号)
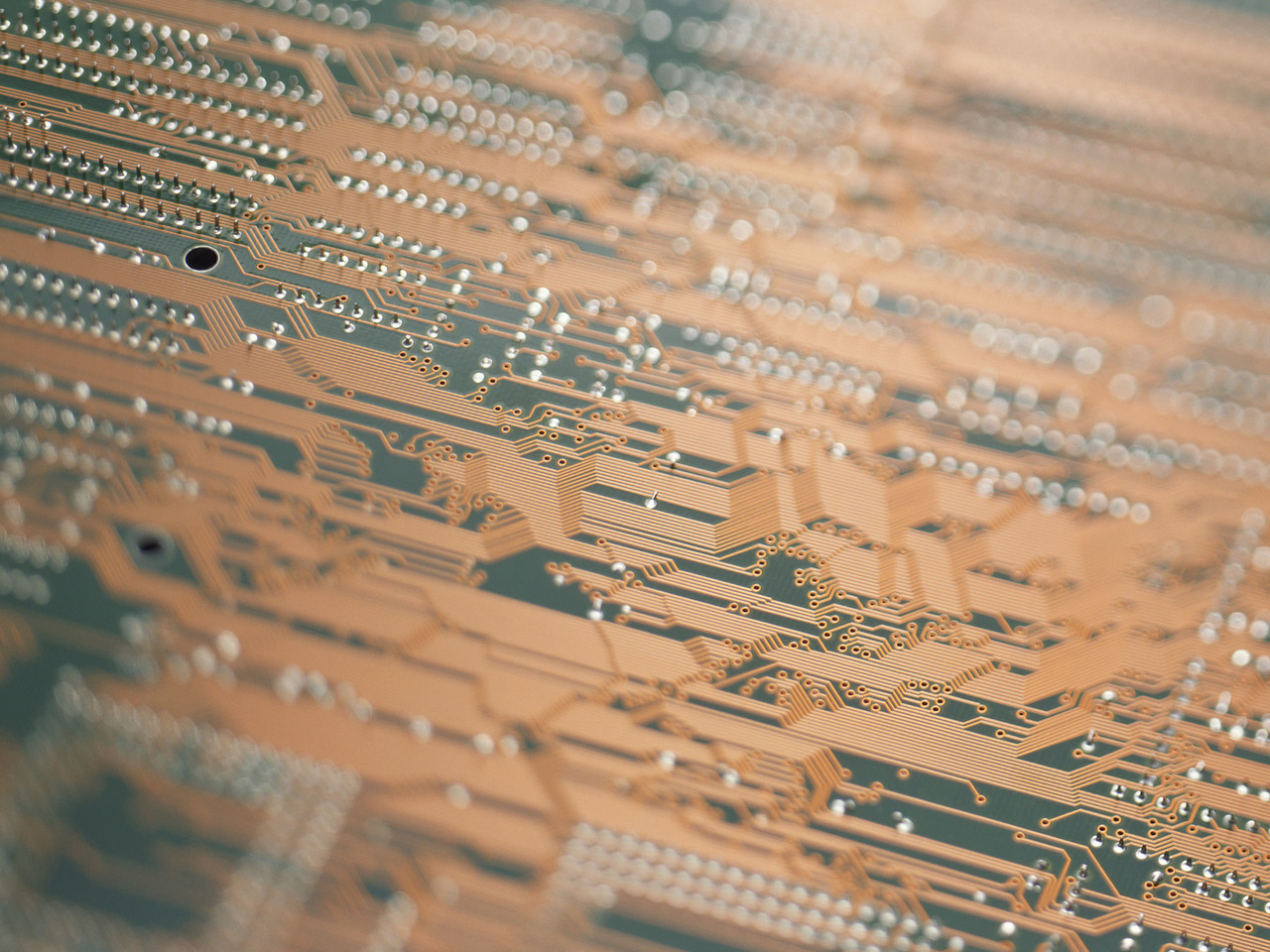
(3)著作権の発生、移転
① 著作者は、著作物を創作することにより、著作者人格権と著作者財産権から構成される
著作権を取得します(第17条)。著作権は、特許権等と異なり行政庁に対する登録は要求
されず、いかなる方式の履行も不要です(第17条2項)。
これを無方式主義といいます。
② 著作権(著作者財産権)は、その全部または一部を譲渡することができます。
(第61条1項)。
この権利は、財産的利益、経済的利益を確保することを目的にしているため、対価を得る
ために譲渡する事が認められています。
これに対して、著作者人格権は、著作者本人に専属し譲渡することができないとされています。
(第59条)。
これは、著作者の著作物に対する精神的な利益―例えば、著作物に対する思い入れ等―を保護
るための権利であるという性質に基づいています。
(4)著作権の存続期間
① 著作権(著作者財産権)は、著作者の死後70年を経過することにより消滅します
(第51条)。
この存続期間には、次のような例外があります。
a 無名・変形の著作物は、公表後70年を経過するまで存続します(第52条1項)。
もっとも、存続期間満了前にその著作者の死後70年を経過していると認められる無名ま
たは変名の著作物の著作権は、その著作者の死後70年を経過したと認められたときに、
消滅するとされています(第52条1項)。
b 団体名義の著作物は、公表後70年を経過するまで存続します(第53条1項)。
しかし、その著作物が創作後70年以内に公表されなかったときは、創作後70年とされ
ています。
c 映画の著作物は、公表後70年を経過するまで存続します(第54条1項)。
しかし、映画の著作物が創作後70年以内に公開されないときには、創作後70年と
なります。
(5)著作権の制限
著作権法は、著作者の権利を保護しつつも、一定の場合は著作権者の権利を制限して著作
物を自由に利用できる場合を定めています。
① 私的使用のための複製(第30条)
著作物は、個人的または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること
を目的としている場合は、一定の場合を除き、著作者の許諾、承諾なく複製する事ができます。
② 引用(第32条)
公表された著作物は引用して利用することができます。公正な慣行に合致するものであり、か
つ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものであるなば、公表さ
公表された著作物を著作者の許諾、承諾なくとも利用する事が可能です。
どの様に場合に引用ができるかは、判例に準拠して判断して行くことになります。
この他にも、著作権者の権利を制限する規定がありますが、紙面の都合上割愛致します。
(6)著作権の侵害
著作物が法律上の正当な権限なしに無断で利用された場合、著作者は次のような対応を
行うことができます。
【特長1】民事上の責任
① 差止請求(第112条)
著作権を侵害された場合は、侵害行為を止めるように差止めを請求することができます。
② 損害賠償請求(民法709条)
著作権を侵害され損害を受けた場合は、損害に関して金銭で賠償を求めることができます。
③ 名誉回復等の措置
著作権を侵害された場合、例えば、新聞への謝罪広告の掲載などのように、名誉・声望を
回復等の措置の請求をすることができます。
【特長2】刑事上の責任
① 著作権侵害罪(第119条)
著作権を侵害する行為は、著作権法上、著作権侵害罪という犯罪とされています。
権利者が告訴を行うことにより、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金に処
せられます。
② 両罰規定(第124条)
著作権を侵害した者が法人等の従業員であるときは、侵害者のみならず使用者である法人
等も罰金刑が科せられます。
著作権業務サポートのご案内はこちらをクリック
ご依頼・ご相談はこちらをクリック


